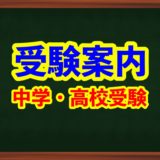小学生の理科の成績は、「理科に興味があるか」で変わってくると思います。
同じことは他の教科にも言えますが、興味があるものは自分から勉強するものです。
そこで、まずはお子様が理科に興味を持つよう工夫をしていく必要がります。
たとえば、すぐ手に取ることが出来る場所に「理科事典」や「理科図鑑」を置いておくと良いでしょう。
リビングのソファーの横などに「理科事典」や「理科図鑑」を置いておくと、テレビのコマーシャルの時に見たりすることがあると思います。
些細なきっかけで理科に興味を持つようになると、成績が上がってくる可能性があります。
お子様が「理科好き」になるよう、仕掛けを作るようにしてみましょう。
目次
理科事典はカラーのものを
お子様に理科に対して興味を持ってもらうために、カラーの理科事典をおすすめします。
白黒の字が沢山書いてある参考書などは、読みたいと思わないのではないでしょうか。
理科に興味を持ってきたら、そういった参考書や教材を準備しても良いかと思います。
最初は、図が多く出ているカラーのものからスタートすることで、お子様に興味を持ってもらいましょう。
- 理科の全分野が収録されています
- 中学生になっても使えると思います
- 科学とありますが、植物や動物も出ています
- カラーのイラスト・写真が多く、小学生向けです
理科事典は大きくて重いものが多いので、持ち運びには不便です。
そこで、リビングのソファーの横やトイレなど、すぐ手に取れる場所に置いておくことがポイントです。
空いている時間にペラペラめくって興味があるページから読んでもらえたら、第一段階は成功でしょう。
理科図鑑もカラーのものを
理科事典と同じ感じもしますが、理科図鑑もカラーのものを準備することをおすすめします。
上記の理科事典は、理科全分野を網羅しています。
そこで、理科図鑑はお子様が興味を持った分野に特化しても良いでしょう。
たとえば、宇宙や天体に興味を持った場合、それに特化した図鑑を与えると更に勉強するかと思います。
そういった積み重ねで、理科という科目が好きになる可能性が高まります。
科目自体を好きになると自分から勉強するようになるので、テストの点数が良くなります。
テストの点数が良いと更にその科目を頑張ろうという気持ちが出てきます。
これが勉強の好循環です。
勉強の悪循環は、好循環の逆で科目が嫌い、テストの点数が悪い、その科目の勉強は後回しになるといった感じです。
- 最初は写真やイラストを見るだけでも良いでしょう
- 解説が少々難しいかもしれません
- 植物分野に特化しています
- 中学受験の役にも立ちます
理科事典よりは若干軽いですが、それでもすぐ手に取れる場所においておくことが大切です。
最初は「勉強」といった感じでなくても構いません。
興味を持ってもらうことにポイントを置きましょう。
隙間時間にペラペラと見てもらえたら成功です。
興味を持ったら少し勉強的要素を取り入れてみる
上記の理科事典や理科図鑑でお子様が興味を持ったら、少し勉強的要素が入っているものを準備してみましょう。
くれぐれも焦らずお子様が興味を持ってからにすることがポイントです。
また、勉強的要素が入っているからといって、無理強いをしてはいけません。
理科を好きになってもらった方が、後々の成績は良くなるかと思います。
引き続きお子様の様子を見ながら対応をしていきましょう。
- 中学入試を意識して作られています
- 基本が多いので、最初の1冊におすすめです
- 1冊持っていると、とても便利です
- 索引で用語を調べることが出来ます
上記の2冊は中学受験を考えているお子様におすすめです。
中学入試の理科は、中学校で習う理科よりも細かい知識を要求されます。
たとえば、「春の七草は?」と聞かれてすぐ答えられますか?
中学受験を目指しているお子様は、しっかりと答えることが出来ると思います。
興味を持っているかいないかで、覚える作業の効率が大きく違ってきますので、まずは興味を持ってもらえるよう色々と工夫をしてみて下さい。
また、知らない用語が出てきた時に、ぱっと調べることが出来るか出来ないかによって、興味を持続することに影響が出てきます。
1冊用語集があると、中学受験の勉強を本格的に始めた際にとても便利です。
まとめ
理科の分野は大きく分けると、「生物」「化学」「地学」「物理」の4分野となります。
どの分野からでも構いませんので、まずはお子様が興味を持った分野から攻めていきましょう。
問題を解かなくても、暗記をしなくても、とにかく最初は怒らないことが重要です。
自分から理科事典や理科図鑑を見ていたら、声かけをしてあげるようにしましょう。
一緒に理科事典や理科図鑑を見ると、保護者の方も楽しめるかもしれません。
それほど最近の理科事典や理科図鑑を面白く作られています。
お子様と一緒に理科に興味を持つと、話が弾むようにもなるものです。
段々と勉強的要素を取り入れないといけませんが、焦ることなじっくりと様子を見てあげるようにしましょう。