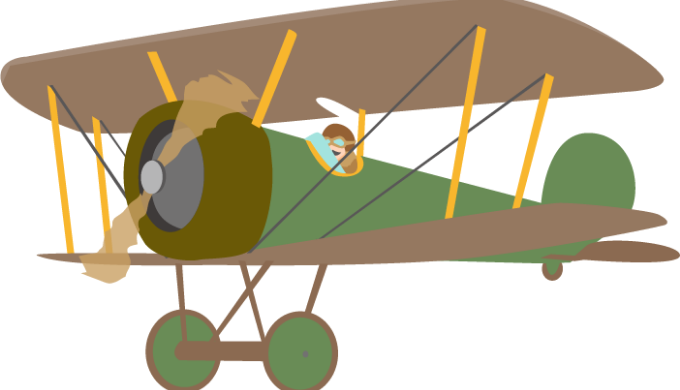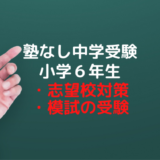第一次世界大戦は、日本から遠く離れたヨーロッパが戦場となったため、歴史の勉強をするまで知らない人が多くいます。
第二次世界大戦につながる部分もありますので、しっかり確認をしておく必要があります。
また、大正デモクラシーという言葉は、そのままでは意味が分からない人が多くいると思います。
大正デモクラシーにとらわれ過ぎず、全体の流れを確認していくことに重きをおきましょう。
前回の内容【中学・高校受験】社会の歴史(明治時代 日清・日露戦争)
それでは、大正デモクラシーと第一次世界大戦についてを確認していきましょう。
大正時代
1912年〜1926年
大正天皇が天皇であった約15年間を大正時代という。
- 大正デモクラシー
- 第一次世界大戦
大正デモクラシーとは
人々の意識が高まり、自分たちの力で世の中を変えようとする運動が起こった。
この動きを大正デモクラシーという。
吉野作造が「民本主義」を唱えた。
大正時代の政治
第一次護憲運動と大正時代の内閣
尾崎行雄や犬養毅らが、「憲政擁護」「閥族打破」をスローガンに、桂内閣の退陣を求める。
明治時代は、総理大臣のほとんどが薩摩・長州藩の出身者のグループ(藩閥)もしくは、公家から選ばれていた。
大隈重信内閣は、第一次世界大戦に参戦し、中国に対し二十一カ条の要求を出した。
寺内正毅内閣は、ロシア革命時にシベリア出兵を行った。
シベリア出兵に備えて米屋が米を買い占めると、米の値段が上がり魚津(富山県)の主婦たちが米屋を襲った。
この動きが全国に拡大し、米騒動が起こった。
原敬内閣は、選挙で選ばれた政党(立憲政友会)の人々を中心とした、日本初の本格的な政党内閣だった。
原敬は「平民宰相」として人気があった。
第二次護憲運動
大正時代の終わりごろ、貴族院出身の清浦奎吾が内閣総理大臣となると、選挙で選ばれていない貴族院出身の清浦内閣は批判を受け、第二次護憲運動が起こった。
普通選挙法と治安維持法
清浦内閣が総辞職した後、加藤高明が内閣総理大臣となった。
加藤内閣は1925年、普通選挙法を成立させた。
同じ1925年、治安維持法が制定された。
普通選挙法
満25歳以上の男子すべてに選挙権が与えられた。
治安維持法
社会主義者が議会に出て活動することを恐れ、社会主義運動を厳しく取り締まるために制定された。
第一次世界大戦
1914年:サラエボ事件
ドイツ・オーストリアなどのグループとイギリス・フランス・ロシアなどのグループが激しく対立していた。
1914年、オーストリアの皇太子夫妻がサラエボでロシア側のセルビア人の青年に暗殺された。(サラエボ事件)
第一次世界大戦の開戦
サラエボ事件をきっかけに、ドイツ・オーストリアを中心とする同盟国と、イギリス・フランス・ロシアを中心とする連合国の間で、第一次世界大戦が始まった。
第一次世界大戦では、「飛行機・戦車・潜水艦・毒ガス」などの新しい武器が使われた。
そのため、死者900万人・負傷者2000万人を出す悲惨な戦争となった。
日本の動き
第一次世界大戦の開戦にともない、日本は日英同盟を理由にドイツに宣戦した。
日本は中国にあるドイツ軍基地を攻撃した。
そして、中国の袁世凱(えんせいがい)大統領に対し、二十一カ条の要求を出した。
ロシア革命が起こる
戦争が長引いたことにより、第一次世界大戦に参加した国の人々の生活は苦しくなっていった。
1917年、ロシアではレーニンを中心として、皇帝をたおす革命(ロシア革命)が起こり、社会主義の政府を作った。
第一次世界大戦後の1922年には、ソビエト社会主義共和国連邦が誕生した。
社会主義とは、財産を国有化し、富を全国民に平等に分けるという考え。
社会主義の考え方が広まることを恐れた日本やアメリカなどの国は、革命をけん制するために、シベリア(ロシア東部)に出兵した。(シベリア出兵)
シベリア出兵は数年間続いたが、失敗に終わった。
アメリカの参戦と第一次世界大戦の終結
第一次世界大戦が始まると、アメリカは中立を保っていたが、途中から連合国側について参戦した。
アメリカは生産力が高く、戦争の流れは連合国側に有利になっていった。
1918年、第一次世界大戦は連合国側の勝利によって終わった。
1919年、パリで講和会議が開かれ、ベルサイユ条約が結ばれた。
- 日本は山東省にあるドイツの権利を引き継ぐ
- 日本が赤道以北の旧ドイツ領の南洋諸島を治めることを認める
朝鮮・中国で起こった運動
第一次世界大戦後、世界では独立を目指す運動が起こった。
日本が支配・進出していた朝鮮や中国でも同じような運動が起こった。
1919年に朝鮮で三・一独立運動、中国で五・四運動が起こった。
国際連盟
1920年、アメリカ大統領のウィルソンの提案により、スイスのジュネーブに本部を置く、国際連盟が作られた。
日本も国際連盟に参加し、新渡戸稲造が事務局次長として活躍した。
アメリカは参加せず。
ドイツ・ロシアも当初は参加が認められず。
大正時代の生活
第一次世界大戦中、日本は重化学工業や海運が発達した。
輸出が輸入を上回る「大戦景気」となり、成金と呼ばれる大金持ちもあわられた。
また、財閥とよばれる大会社は大きな利益をあげた。
関東大震災(1923年)
1923年9月1日にマグニチュード7.9の大地震が関東地方を襲った。
地震の発生時間がお昼時だったため、大規模な火災が発生し、10万人以上の犠牲者が出た。
震災の混乱中、民衆によって朝鮮や中国の人々が襲われる事件も起こった。
社会運動
都市部:工場で働く労働者が地位や権利の向上を求めて労働運動を起こした。
農村部:土地を持つ地主に対し、地主から土地を借りて小作料を払う貧しい小作農が、地位の安定や小作料を減らすことなどを求めて小作争議を起こした。
女性運動:女性に対する差別をなくし、婦人参政権を求める運動が起こった。
平塚雷鳥・市川房枝が中心に創刊した
全国水平社:江戸時代から続く差別に苦しんだ人々が1922年に全国水平社を結成した。
社会主義運動:日本でも社会主義への関心が高まった。
ラジオ放送(1925年)
1925年に、ラジオ放送が開始され、情報が素早く伝えられるようになった。
大正時代の文化
文学
芥川龍之介
平塚雷鳥・市川房枝:雑誌の「青鞜(せいとう)」
建築物
東京駅の駅舎
まとめ
大正時代の出来事、第一次世界大戦についてを確認してきました。
大正時代の出来事については興味を持ちにくいかもしれません。
漫画で流れを確認しておくのも手です。
絵があるとイメージがしやすくなるので、困った時は歴史漫画に戻ってみましょう。
歴史の勉強もあと少しとなります。
最後まで頑張って、歴史分野でしっかり得点出来るようにしましょう。